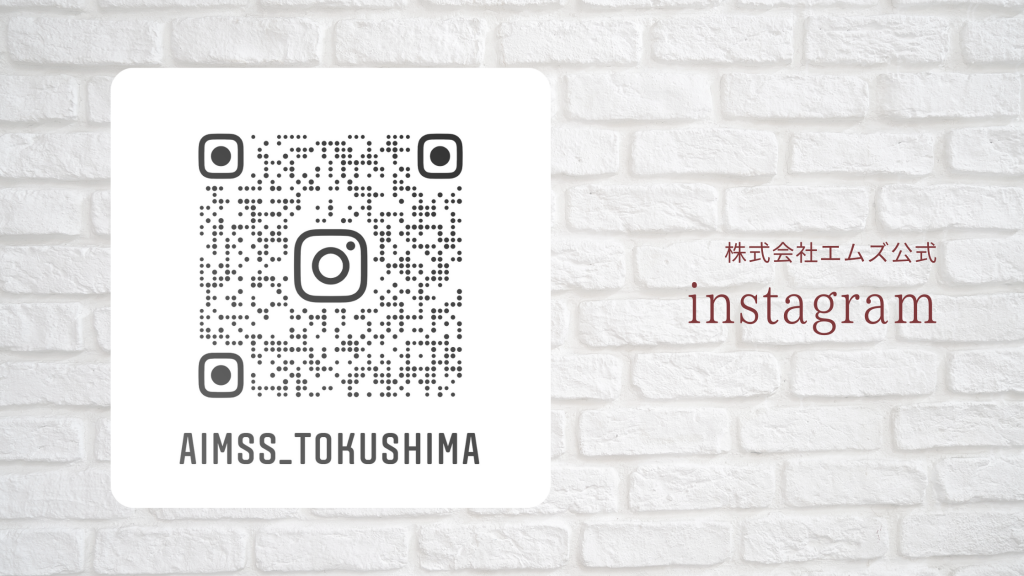こんにちは!スタッフの野田です。
日曜日は、エムズイベント「お抹茶を楽しもう~茶事の形式を一部取り入れて~」の会でした。
石井先生のご自宅に茶室があり、お邪魔させていただいての出張イベント。
今回もたくさんの方にご参加いただき、すぐに満員御礼となりました!
茶道は経験のない私・・・・ドキドキ
まずは門や玄関が開いているかいないかで、入っていいかどうかを確認するそうです。
扉をすかしてくださっていたので、入ってよし!の合図です。
入ると、扉の向こうに「寄付」の文字が見えます。
「きふ」・・・????いいえ、「よせつけ」です。
この「寄付」というお部屋では、コート等をたたんだり、ソックス等をはきかえ身支度を
整える場所です。
 今回は、石井先生のご自宅でしたので、リビングを「寄付」のお部屋として使用させていただきました。
今回は、石井先生のご自宅でしたので、リビングを「寄付」のお部屋として使用させていただきました。
ここで少し今日のお茶席の話を先生からご説明いただきまして、
身支度が済んだ方から順番に、「待合」のお部屋へ移ります。



 「待合」のお部屋では、同席の方との挨拶をおこない、掛物やお花等、お部屋の設えを観て楽しみます。
「待合」のお部屋では、同席の方との挨拶をおこない、掛物やお花等、お部屋の設えを観て楽しみます。
また、お正客とお末を決め、スムーズにお茶席が進むように客の中でも相談をします。
「お正客(おしょうきゃく)」というのは、お客様の中で中心になってもらう人物です。
リーダーとなる重要なポジションなので、今回はお茶の先生でもあるお客様にお願いをいたしました。
また、「お末(おばつ)」とは最後に座った人を指し、
汲み出しのお茶等出されたものをみなさんに配ったり、飲み終えたら入口付近に片付けたり・・・・と
「半東(はんとう)」さんのお手伝いをします。(半東さんとは、お茶席のお手伝いさんのことをさします。)
半東さんから合図があると、「腰掛待合」に移りますが、今回は省略して、
「蹲踞」(つくばい)で、茶室に入る前に心身を清めます。

左・右と手を清め、もう一度すくい口を清め、残り水で柄杓の柄を清めます。
柄杓は、蹲踞では横に傾けて置くのが基本だそうです。


清め終わった方から順に躙口(にじりぐち)より茶室に入ります。
よく見たことのある、あのかがんで入る入口です。
ここまででも、たくさんの作法があり、大変勉強になりました。
いよいよ本番です。

お正客さんから順番に菓子とお茶がまわってきます。
「お先です。」と言いながらいただき、次の方へ回していく様もみなさんとても素敵でした。
今回お茶をたててくださったのは、石井先生の姪孫さん。
先生曰く、若いので手首を使うのがお上手で、お茶の泡立ちが大変きめ細やかだそうです。

すみません。一口いただいた後ですが写真を撮り忘れていた!と思い・・・・(笑)
本当にきめ細やかで、クリーミーでした。甘さも感じるほど・・・
茶と湯の配分、湯の温度等で全く味は変わってくるそうです。

せっかくなので、ご参加いただいた皆さんにも抹茶をたてていただきました!
縦にシャカシャカシャカと手首を使ってたてていくのですが、
ときわさんのように上手く細やかな泡にならず、ポツポツとところどころ大きい泡が目立ちます・・・
ときわさんに聞くと、ポツポツをなくすように、最後は上のほうでゆっくりとたてるそうです・・・・
コツがあるんですね・・・
美味しいお抹茶とお茶菓子をいただき、作法も学べて大変貴重な経験ができました!

お昼はなんと石井先生がお寿司とお吸い物をご準備してくださっていました!( ;∀;)
お客様全員とスタッフ全員分・・・( ;∀;)
手作りの新ショウガの甘酢もとても美味しくて、、、最後の最後まで先生のおもてなしの心に感激いしました。
日本のおもてなしの心は、長く昔から大切にされてきたもので誇りを持って伝えていきたいひとつの文化ですよね。
今回お抹茶の会に参加させていただきそのように深く感じました。。。
石井先生、ときわ先生、ありがとうございました。
また、今回お茶席として使用させていただいた茶室。お庭や蹲踞なども含めて30年前にエムズで設計・建築させていただいたものなんです。
お庭もお手入れが行き届いていて、素敵でした。
愛着を持って大切に過ごしていただいているだけで、とてもうれしく思いますね。
また、30年前に設計した社長にとっては、そこでこのようなイベントができるとは夢にも思っていなかったでしょうね!なんて素敵なお話・・・・と、いちエムズスタッフとして胸が熱くなりました。
「また季節を変えて、お茶の会をしてほしい!」とのお声を多数いただきましたので
石井先生にもご協力いただき、秋冬を楽しんでいただけるようなお茶会ができるといいなと思います。
大変人気のお教室で、すぐに満員御礼になりましたので
また開催される際はお早めのご予約を!!!